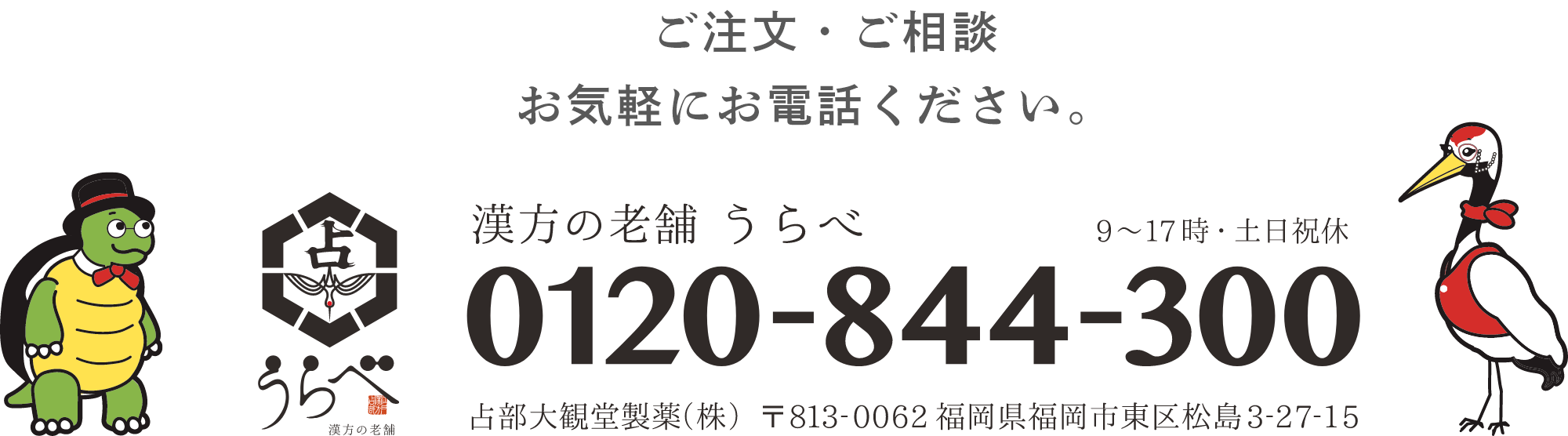更年期とお酒 健康的な付き合い方
更年期を迎えると、ホルモンバランスの変化により体調にさまざまな影響が現れます。
心身の健康に変化が起きやすく、不安定にもなりやすいこの時期は、健康維持のために日々の生活習慣はとても大切です。
特にこの年代で見直したいのが、お酒との付き合い方。お酒を通してリラックスのひとときや、友人とのコミュニケーションを楽しむ方も多いのではないでしょうか。
しかし、心身の変化が起きやすい更年期世代は、それまでのお酒の量や飲み方が与える影響も大きく変わることもあります。
お酒の健康への影響や、上手に付き合うためのポイントについて、今一度見直してみましょう。
更年期のお酒と、健康の関係
1. ホルモンバランスとお酒の関係
更年期を迎えると、女性はエストロゲン(女性ホルモン)が急激に減少し、体内でさまざまな変化が起こります。
エストロゲンは血管や神経系、心臓、骨などに影響を与えるため、このホルモンの減少は体調に大きく関わります。
お酒はリラックス効果があるので、少量であれば一時的にストレス軽減やリフレッシュに役立つ場合もありますが、過剰摂取はホルモンバランスを乱すことにつながりかねません。
例えば、過剰なアルコール摂取は肝機能を弱め、肝臓がホルモンを適切に代謝する働きを妨げる可能性があります。
これがエストロゲンやテストステロンといったホルモンのバランスを崩す原因となり、さらなる体調不良を引き起こすことがあります。
更年期世代は、体の不調に加えて、お酒の影響もでると体がどんどんつらくなりますので、要注意です。
男性も更年期に突入するとテストステロンの低下が見られ、これはエネルギー不足や精神的不安定を招くことがあります。そこに過剰なアルコール摂取による不調が加わると健康維持が難しくなります。
2. アルコールと自律神経
更年期には自律神経の乱れも一因となり、体調不良や気分の浮き沈みを感じることがあります。
自律神経は体温調節、心拍、血圧の調整を行う重要な役割を担っており、このバランスが崩れると様々な不調が現れるのです。
お酒には、一時的にリラックス作用があるため、短期的には心身の緊張をほぐすことに役立つかもしれませんが、アルコールを過剰に摂取すると自律神経の乱れが増し、睡眠の質に悪影響を与えることも。
さらに、お酒は血管を拡張させる働きがあるため、ホットフラッシュ(のぼせや発汗)を引き起こしやすくなることもあります。
また、就寝前の飲酒は、寝つきが悪くなり睡眠の質が低下することが多々ありますのでお気を付けください。
3. 健康リスクの増加
更年期の症状として、心血管系のリスクが増すことがあります。
これは、ホルモンの変動により、血管が硬くなり、血圧が上昇する傾向があるためです。
お酒の過剰摂取は、高血圧や動脈硬化、心臓病のリスクを高める可能性があります。
心血管系に不安を抱えている場合は、アルコールの摂取を控えめにし、健康的な飲み方を心がけることが重要です。

お酒と上手に付き合うためのポイント
1. 適量を守る
更年期に関わらずどの世代においても、最も大切なのは「適量」を守ることです。過剰な飲酒は体に悪影響を与えます。
一般的に、健康的な成人における適量としては、1日1~2杯程度(女性の場合はワインならグラス1杯、男性は2杯まで)が目安ですが、体調によって調整するのが良いです。
不安があるときは飲酒を控え、ノンアルコールドリンクを活用しましょう。
2. 食事と一緒に楽しむ
空腹でお酒を飲むと、アルコールが急激に吸収され、体に大きな負担がかかります。
そこで、食事と一緒に摂ることで、アルコールの吸収が緩やかになり、肝臓への負担を軽減することができます。
3. お酒の種類に気をつける
ワインや日本酒、ビールなどのお酒にはそれぞれ特性がありますが、特にアルコール度数が高いお酒を大量に摂取することは避けましょう。
また、カクテルや甘いリキュールは糖分が多く含まれているため、肥満や血糖値の上昇が気になる場合は控えめにするのがおすすめ。
アルコール度数が低いお酒や、糖分の少ない飲み物を選ぶことが望ましいです。
アルコール度数が低く、糖分の少ないお酒は、蒸留酒である「ウイスキー」「焼酎」「ウォッカ」など。これらは糖質をほとんど含みませんが、アルコール度数が高いため、ロック、水割り、ソーダ割りなど、割り材を工夫して飲むのがおすすめです。
4. お酒を飲む時間帯を工夫する
お酒を飲む時間帯も重要なポイントです。
夜遅くの飲酒は、睡眠の質に影響を与えます。特に就寝前のアルコールは、寝つきを良くするものの、深い眠りを妨げることがあります。
お酒を楽しんだ後すぐ就寝するのではなく、体と胃腸を休める時間をとってから就寝するのが望ましいでしょう。
5. リラックスできる方法と併せて取り入れる
お酒を楽しむ時間は、心身をリラックスさせる大切なひとときですが、お酒に頼りすぎることは避けましょう。
お酒以外のリラックスに、ヨガや深呼吸、散歩なども有効です。お酒を飲む時間と合わせて、心身をケアできる時間を持つことで、健康の維持に役立ちます。

まとめ
更年期世代にとって、健康的にお酒と付き合うことは健康維持のために大切なポイントです。
更年期は体調の変化が現れやすい時期ですが、正しい生活習慣を取り入れることで、健康を保ちながら元気に過ごすことができます。
「酒は百薬の長」とも申します。
お酒を楽しむためにも、日々の生活の中でバランスを取っていくことが、健康寿命を長く保つための秘訣です。
◆福岡で230年超の歴史 漢方の老舗うらべ◆
※漢方の老舗うらべ 通販公式サイト うらべのうらら
参考
https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/hypertension-2/
https://e-kennet.mhlw.go.jp/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/leaf-alcohol-male.pdf
https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/alcohol/health-01.html